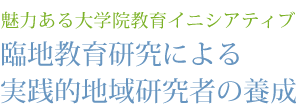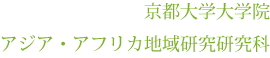総合討論の報告(2/3)
2. 質問票をもとにした発表者との討論
続いて5人の発表者の方に、会場からの質問票に答えていただきました(予め会場の参加者には質問票をお配りし、総合討論の前に提出していただきました)。
■司会
最初の質問は、「実践的地域研究」の成果の、調査対象地域へのフィードバックに関してです。ポイントは2つあります。1点目は、研究成果の開示について。2点目は、公表した研究成果のネガティブな効果が出たときに、実践的地域研究者はどう対応をとるのか、ということです。
では、東城さん、そして小國さんにお答えいただきたいと思います。
■東城文柄
では、ご質問には一般論ではなくて、私の研究をどう現地にフィードバックしていくのか、というお話しでお答えしたいと思います。私の扱っていた事例は、非常に生々しい話で、じっさいに森林面積の減少が住民(ガロ)の人為によって起こっているのかいないのか、という話です。8,000ヘクタール以上の領域に10,000世帯前後の住民が関わっています。もちろん、政府が全世帯を公園区域に指定したところで実力で追い出せるわけではないので、それでどうこうという話ではないのですけれど、政府がエコ・パークという、境界壁で囲い込んだ国立公園の保護を強化するような施設を作って、それが作られたことによって、それまでも立ち退きの圧力をかけられていた現地住民に、これはほんとうに追い出されるかもしれないという危機感が重なって、発表で報告したような反対運動が起こっていったという、社会状況のもとでの調査だったわけです。
私の研究ではそういう状況に対して、もともと森林に住民がいて、そこにどちらかと言えば、後から政府が入ってきて理不尽なことを言っているのではないかという、かなり明確に地域住民の側に立って、研究結果をああいうふうに提示しています。
ただ、指導教員にときどき注意されることというのは、今日発表でお見せした以外にも、研究全体のなかでは地元住民の移住史などのデータも扱っていまして、読みようによっては、1950年代とか60年代といったきわどい時期に移住してきた人たちについては、(政府が)かれらを「侵入者」と強引に言えば言えなくもないのではないか、ということです。つまりパブリッシュということに関しては、自分の発表データというものがどういう影響を持ってしまうのかということをよく考慮してなされなければならない、ということはつねに意識するようにしています。
研究の成果の対象地域へのフィードバックということに関しては、研究成果を日本文だけではなくて英文で論文にして出したいと思っています。現地でお世話になった人びと、反対運動の担い手の方にも、成果が形になったら送って欲しいと言われているので、そういった交流はこれからも続けていこうということを考えています。
それで、ネガティブな効果が出てしまうとどうするのか、ということに関してですが、それを言われるともうなにもできなくなってしまうと言いますか、ただ、そういう効果、影響の可能性を念頭において、センシティブになりながらなにかやっていくしかない、と申しあげるしかありません。
■司会
ちょっと、東城さんに私のほうから補足的にお聞きしたいんですが、峯さんのコメントにあった「政治的コンテクスト」に関してです。
ご発表やいまの質問に対するお答えを聞いていますと、非常にセンシティブなフィールドで調査研究をなさっているということがわかります。森林保護区(あるいはエコ・パーク指定区域)をめぐって、かなり明確な対立がげんにある、という風に受け取っているんですが、おそらく現場でおこっていることというのは、「現地住民VS. 政府」という単純なことだけではなくて、(反対する)住民のなかにもいろんな立場の人やグループがあって、かたや公園側というのも「政府」という一枚岩のものではない。
そのなかで、東城さんは積極的に、英文で研究成果を公表していこうと、つまり、現地の人びとの一部が読める言語で成果を発表しようとされているわけなんですが、そのインパクトはどういったものになるのでしょう。もちろんインパクトというのは正か負か、という二つだけではなくて、それぞれの立場の人たちがそれぞれに読むような、必ずそういったインパクトを与えることになるんじゃないかと思うんです。
そこで、今日のご発表のような内容を英文で発表されたときに、具体的に、どのようなインパクトを現地の状況に与えることになるのかという点について、どういうかんじで見通しておられるのか、お聞きしたいです。
■東城文柄
まず、ご指摘のようにもちろん住民というのも一枚岩ではありません。たとえばげんに、反対運動のグループのうち三分の一のメンバーが、政府との折衝を進めていくなかで、グループからはなれ、どちらかといえば政府寄りになって、急に「反対運動の人びとは環境のことを考えていない」と言い出したり、というような経緯もありました。
そういったことを考えて、いま私が考えているのは、論文の書き方です。「現地住民VS. 政府」のような対立の構図ばかりを表面に出してしまうと、どうしてもそちらの方に(読み手の側の)議論が集中してしまいます。そういった論争や対立は、もちろんこの研究の背景にはあるのだけども、私が問題として焦点を当てたいのは、森林という空間がどういう風に考えられるのか、というところなのです。単純に森林が減少したとかしないとかではなくて、そこでそれまで長いあいだ生活してきた人がどのように森林と多様な関わりをもってきたのかということ、そこを考えていくと(単純に「森林=自然」というものではなくて)もっと森林というものが複雑な意味や機能をもった空間なのだということがわかる。この点を強調するような書き方で論文を書こうと思っています。現場での論争や対立が、こうした認識をふまえずに非常に単純化された議論がなされているのではないか、というのが私の見方だからです。そのためには、いま現場で行われている論争、住民は「侵入者」であるのかないのか、などの論争であまり論拠として使われないような資料をもちいるのが ひとつ有効なやり方ではないかと思っていまして、たとえば私が衛星画像をデータとして積極的に使っているのはそういう意図もあります。
■小國和子
1点目の「対象地域への成果のフィードバック」に関してですが、まずその「フィードバック」という考え方についてお話しします。私自身にとって、対象地域との関わり、たとえば農村開発支援で関わる、調査で関わるということは、つねに経過であって、いまもつねに関わり続けている、という意識をもっています。その意識でいきますと、なにかの区切りで成果ができて、それで終わり、というのではなくて、そのとき訪問のつどにつねになにか新しいことが起こっていて、それに対して私も意見を出す、というような関わりを続けています。これが私にとっての広い意味での「関わり」です。
狭い意味で、単純に成果(書いたもの)のフィードバック、という意味で言いますと、書いたものがあったらそれを村に持っていって村で説明する、というようなことは当然なされるものだと思います。ただここで、「調査対象者」へのフィードバック、と言ったときに、その「対象者」というのは、村びとだけではなくて、現地の行政であったり、開発支援の機関に対するフィードバック、これも「調査対象者」へのフィードバックであり、これらをきちんとやることは、重要だと思います。
もう少し具体的に言いますと、たとえば批判的な研究をやったときに、その成果をアカデミズムのなかでだけ公表して、そうしたさまざまな方面へのフィードバックはしない、というやり方は、フェアじゃないと思うんです。とにかく、対象地域でかかわっている開発支援の機関があったならば、批判的な研究はまずその機関の内部で議論する、くらいのことをやるのが本来なんじゃないかと思います。
2点目の、ネガティブな影響を与えてしまったとき、ということに関してですが、さきほどの東城さんのおこたえが、ものすごく誠実で共感できるものでした。というのも、ネガティブな影響が出たら困るから「かかわらない」という選択肢は、すでにいったん関わっていて、これからも関わるだろうという人間にとってはないわけです。関わっていくなかで、もちろん全部がうまくいくとか、そういうことはありませんから、うまくいかなかったところに関しては、責任もってそれはなんとかしていきましょう、と言うしかないですね。
もちろん、東城さんもおっしゃったように、政治的なものに絡め取られながらもそのなかでつねに最善のことをやっていく、ということを、センシティブになりながらやっていくしかないと思います。
■司会
ありがとうございました。
では二件目の質問です。これは(研究にたいする)ニーズの問題です。「現地住民」の多様性、現地の社会関係の複雑さを鑑みて、「地域の問題」「地域のニーズ」を一括して論じることができるのか、という質問です。
この質問に関して、まず、黒崎さん、岩井さんにお聞きすることにします。
■黒崎龍悟
たしかに、ご指摘の現地住民は一枚岩ではないということは、みなさんの共通認識だと思います。しかし、そのなかでも、 (現地のニーズに関する)住民の間での共通了解のようなものがないわけではないです。もちろん、そうした共通のなにかも、固定的なものではなくて時間とともに変わっていくものです。しかし、人びとの意見やニーズといったものがぜんぶバラバラというわけではなくて、地域の人びとのなかに、明確ではないにしろなにかの輪郭をもったニーズのようなものがある、というのが私の見方です。
(「実践的」であるためには)そうしたニーズをできるだけセンシティブに組み入れていくことが必要ですし、そのためには研究者自身が関わっていき、そのネガティブなフィードバック込みでの関わりのプロセスを共有するという姿勢をもつことが大事だと考えています。
■岩井雪乃
黒崎さんと同意見で、住民は非常に多様であって、しかしそのニーズをまとめていくことは基本的には大切で、同時にまた非常に難しいところだと思います。
ただ、イベント分析のようなやり方で、ちょっとしたなにかの出来事が起こったときに、そのようなあるていどまとまった意見のようなものがぱっと見えてくることはあると思います。そういった機会をいくつか重ねていくうちに、さきほど重田さんがおっしゃった「共感」のようなかたちで、まとまりが理解されていくように考えています。
■司会
ありがとうございます。
ところで、つぎに甲山さんにお聞きしたいのですが、ご発表のあとに、座長(嶋村)のほうから、甲山さんの研究は、誰のニーズにこたえてようとしているものなんですか、という問いかけがあったと思います。そこで甲山さんがお答えになったのは、現地の人びとのニーズにこたえるもの、ということでした。今日ご発表の方々のなかで、甲山さんのご研究はどちらかといえば理系的、「科学的」な内容のものであるように受け取ったのですが、現地の人びとのニーズを把握していくために、研究者の側がやっていることというのは、どのようなことなのでしょうか。
■甲山治
まず、すべてが(現地の)ニーズを探るところから入るわけではないということはあります。今回発表した研究は、現地の機関の要請で共同研究に加わっているんですけども、もちろん調査をすすめていくなかで、調査者である私自身が見つけていくニーズというのがあると思います。ですから、いまのところ、現地機関の人びとといっしょに調査をすすめていくなかでニーズを見つけていこう、ということがあるくらいですね。
その意味で、(社会開発研究のように)「まず、現地のニーズをさがす作業ありき」というわけではないのは、今回の私の研究に関するかぎりはそうです。私のような研究の場合には、まずこちらがもっている技術があって、こんなことやあんなことができますよ、と言ったときに、じゃあこういうことをやりたい、というような形で調査をすすめながらの過程でニーズが出てくることが多いです。今回の研究のケースもそうです。ですから、ある意味では現地のニーズを探る、という点で努力を怠っているところがあるのかもしれません。
ただ、石田さんがコメントでおっしゃった「気軽に」ではありませんが、現地に入って、そこで自分のできることをさがす、という作業には、まず最初にニーズの発掘に取り組んでそれから調査というやり方もあるし、調査をしながらニーズの発掘に取り組んでいく、というやり方もあると、当面はそう楽観的に構えながら研究をしています。
■司会
ありがとうございました。
「ニーズ」というのは、今日の5人の方々のご発表とこれまでの議論の内容からしますと、「実践的地域研究」を考えるときに、ひとつのカギになるのかもしれないと思います。
「実践的」というからには、やはり、学術的に貢献する、あるいは学説史上の問題にあらたな知見を加えていく、といった、研究そのものからくるニーズにこたえるだけではなくて、現実社会のどこかにニーズがあって、それに向かって研究者がなにか貢献する、という企図をもってなされるものなのではないか、と考えることができます。
しかし、じつはこのニーズというものは、最初からどこかに「ある」ものではなくて、対象としている地域ですとか、そこの人びとと研究者との関わりのなかで、できていくものなのではないか、と思うんです。となると、実践的地域研究にとりくんでいく以上は、やはりこのニーズができていく過程そのものも、慎重に考えなければいけないことです。というのも、地域研究のおもしろさはどこにあるかといえば、やはり「共感のダイナミズム」にあると思いまして、これはコメンテイターの方々もおっしゃっていた住民の視点、当事者性などの話とも関係します。ですが、それは同時に地域研究者の弱点のひとつとして言われるところでもあると思います。つまり、フィールドワークで実際に現地に入って、「現地の人びとはこう言っていた」「私はじっさいに見た」、というところにもとづく素朴な「理解」の陥るかもしれないちょっとした錯誤、誤りのようなものもじっさいにあると思います。ですから成果の発表と「政治的コンテクスト」の問題同様に、「研究にたいするニーズのできていく過程」も、かなり慎重に吟味することが必要なことではないかと思います。