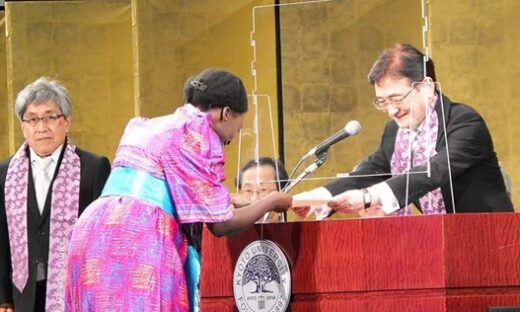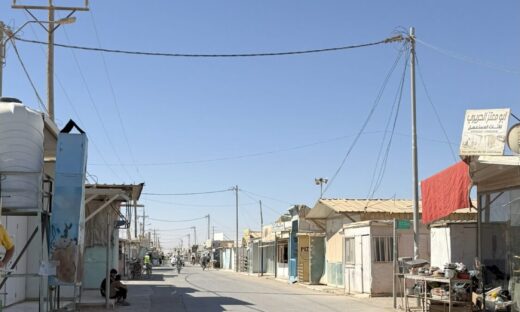アジア・アフリカ地域研究情報マガジン 第264号

■■■ June 2025 第264号 ■■■■■■■■■■■■
アジア・アフリカ地域研究情報マガジン
ASAFAS INFOrmation Magazine
https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/
■■■■■■■■■■■■【発行部数1135】■■■■
__今月号の目次 Contents__________________
□ フィールド便り…………. 「牛が帰って行く時間」
□ メルマガ写真館…………. 「消えゆく氷と湖」
□お知らせ………………. グローバル地域研究専攻2025年度第3回オープンキャンパス、 第266回アフリカ研究地域研究会、2025年度第1回「インドの将来」研究会開催 (ダイキン・ASAFAS産学共同研究)
□ 最近の出来事………………… Facebook・X(旧Twitter)情報
□ 編集子より
_______________________________
==========================================================
■ フィールド便り Letter from the Field
==========================================================
「牛が帰って行く時間」
緑川茉歩(グローバル地域研究専攻)
村で生活をしているとき、「ゴードゥリ(gau-dhuli)」という言葉を教えてもらいました。「ゴー(gau)」は牛、「ドゥリ(dhuli)」は砂ぼこりを指す言葉なのですが、2つの単語を繋げると「夕方」、「黄昏時」という意味になるそうです。
私がフィールドワーク中に滞在していたインド・グジャラート州では、たくさんの牛が飼育されています。今では家のそばで飼われている牛が多いのですが、かつては牧畜カーストの人々によって伝統的な飼育方法が営まれていました。彼らは、村の家から牛を預かると、昼間は放牧させて夕方頃に牛と一緒に家に帰ります。長い棒を持った牛飼い人に急
かされて、牛は早歩きで帰路を急ぎます。この時、牛の足元で巻き上げられる砂ぼこりがゴードゥリです。そして、ゴードゥリが発生する時間というのが夕暮れ時なのです。
言葉はその国の文化をそのまま反映します。「夕方=牛が帰って行く時間」と結び付かられるほど、インド社会において牛の群れは当たり前の風景であることがわかります。
グジャラート州の夕日はゴードゥリの言葉の美しさと並ぶほど綺麗なものでした。そろそろ畑仕事が終わるかという時間、空が徐々にオレンジ色に染まっていきます。アーナンド市からアーメダバードに戻る道中、その日も車内から夕日に見とれていました。その時、同行していた方に日本との夕陽の見え方の違いについて指摘されました。
「日本で夕日を直接見たことある?」。最初に聞かれた時には意味がよく分かりませんでした。しかし、目の前にあるインドの夕日を見ながら考えると確かに大きな違いがありました。インドの夕日はくっきりと丸く、まるまるとオレンジ色に輝いているのがよくわかります。確かに、日本の夕日はもっとぼんやりとしたイメージがあります。
どうしてインドの夕日は直接見えるのでしょうか?それは大気汚染が原因だそうです。大気中に大量の物質が蔓延しているため、夕日の光が私たちの目に届くまでの間、その強い光が徐々に弱められていくのです。逆に言えば、日本は空気が綺麗ということなのでしょう。
アーメダバードの大気汚染は、デリーについで凄まじいものです。インドの大気汚染の話はしばしば話題になるものですが、夕日の見え方として実感できることに驚きました。
大気汚染の原因は工場や車のガス、焼畑の煙、砂漠から来る砂塵など様々ありますが、農村部で発生する砂ぼこりはウシの大群と共にあります。
夕方、牛、巻き上げられる砂ぼこり。この風景は農村部の懐かしい景色の一つです。赤々と照らす夕日の中、ウシたちが自分の家に帰って行きます。
写真1:牛の餌を運ぶ。
写真2:オス牛が荷物を運ぶ。
写真3:夕方のおやつ。
(上記フィールド便りに関する写真は次のFacebookでご覧ください。)
https://www.facebook.com/asian.african.area.studies/posts/
pfbid026V4W3aEsSVsemgyeTXCAs4PNG9LCrkcU4LqmTMZzdEn2MHZrYAyLNoLKX5hQGK9gl
==========================================================
■ メルマガ写真館 Photo Gallery
==========================================================
「消えゆく氷と湖」
吉田巖嗣(グローバル地域研究専攻)
「ここには10年前までは湖があった、氷もあった」とB. ラマ氏は言いました。わたしたちは東ネパール、ヌンブール・ヒマールのふところに抱かれた氷河湖の縁から、干上がりかけた谷を見下ろしていました。ドゥックンダ(乳の池)とよばれるこの湖の一帯は、人里離れた標高4,600mの高地に位置しますが、毎年夏にはシャーマンに先導された人びとが集まり、祭礼を繰り広げる場でもあります。足元をみると、岩と砂のあいだに亀裂が走っています。氷が溶けたせいか、岩が動き出しているというのです。
この湖の縁がひとたび決壊すれば、ドゥックンダの水は隣の涸れ谷へとあふれ出してしまうでしょう。B. ラマ氏はそのことを不安げに語りました。
写真1:ドゥックンダ、乳の池
写真2: 地表の亀裂
(上記メルマガ写真館に関する写真は次のFacebookでご覧ください。)
https://www.facebook.com/asian.african.area.studies/posts/
pfbid0d1U4AF9WfuY2jRXNpWkommV8wVY4NGt677nTTbgFLA1owRb6mhHmtpcJkKBmWNECl
(過去のメルマガ写真館は、次のURLからご覧いただけます。)
https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/photoessay/
────────────────
□ お知らせ
────────────────
◆グローバル地域研究専攻2025年度第3回オープンキャンパス
日時:2025年7月2日(水)13:30-17:00
参加申込URL:https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/oc/global2025_0702/
*オンライン会議システムZoomでの開催となります。
◆ 第266回アフリカ研究地域研究会(7月17日(木))開催
日時: 2025年7月17日(木)15:00-17:00
場所: 京都大学稲盛財団記念館3階 大会議室
演題:戦争の傷跡を超えて コンゴの商人たちが拓く復興への道筋
講師:高村 伸吾
要旨:コンゴ民主共和国では、「アフリカ大戦」とも称される大規模な紛争により、540万以上の死者を出し、現在もM23の武装蜂起など依然として不安定な情勢が続いている。国家の機能が十分に及ばず、国際社会の支援も限定的な紛争後の社会において、人々は独自の知識や技術を駆使しながら復興への道筋を模索している。本発表では、このような状況下で活躍する商人たちに焦点を当て、彼らがどのように社会再建に寄与しているのかを検討する。
申込:オンラインでの受講は要事前申し込み
連絡先:
Email) caasas@jambo.africa.kyoto-u.ac.jp
電話)075-753-7803
Web site) http://www.africa.kyoto-u.ac.jp/
備考:共催:京都大学アフリカ地域研究資料センター/日本アフリカ学会関西支部
◆ 2025年度第1回「インドの将来」研究会開催 (ダイキン・ASAFAS産学共同研究)
日時:2025年7月7日(月)10:30-12:00
場所:京都大学 吉田キャンパス 総合研究2号館 4階 Conference Room(AA463)
形式:ハイブリッド形式(対面+Zoomによるオンライン参加)
講演タイトル:「インドの「普通」の住宅:中庭・環境・住経験」
講師:柳沢究 (京都大学大学院工学研究科建築学専攻 准教授)
*研究会ポスター(お申し込みはポスター下のURL、QRコードより): https://www.global.asafas.kyoto-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2025/06/478c6875c184b845cad24d08f43de522.pdf
────────────────
□ Facebook・X(旧Twitter)情報
────────────────
FacebookとX(旧Twitter)から最新情報を発信しています。
是非ご登録ください!
○ 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科(ASAFAS)
https://www.facebook.com/asian.african.area.studies/
https://twitter.com/asafasprcc
○ 東南アジア地域研究専攻Facebook
https://www.facebook.com/AsafasAsia/
○ 東南アジア地域研究専攻生態環境論講座Facebook
https://www.facebook.com/asaseaeco/
○ アフリカ地域研究専攻 Facebook
https://www.facebook.com/ASAFASAfrica
○ グローバル地域研究専攻Facebook
https://www.facebook.com/京大アジアアフリカ地域研究研究科グローバル地域研究専攻-545053518980616/
○ 京都大学アフリカ地域研究資料センター
https://www.facebook.com/CAASKyotoUniv/
http://twitter.com/Africa_Kyoto_U
http://twilog.org/Africa_Kyoto_U
==========================================================
■ 編集子より From the Editor
==========================================================
京都の夏が始まり、若き院生たちは、ぞくぞくと世界へ飛び立ちます。
私はと言えば、冷房と「小泉文夫・世界の民族音楽」で異邦の地へ音楽トリップ。
旅に出られぬ者にも、旅する方法はあるのです(負け惜しみではなく)。(H・I)
==========================================================
□ メールマガジンに対するご意見・ご感想お待ちしております。
http://form.mag2.com/gianoubima
==========================================================
◆ このメールマガジンは、京都大学大学院アジア・アフリカ地域
研究研究科(ASAFAS)広報委員会、ASAFASキャリア・ディベロップ
メント室、ASAFAS臨地教育・国際連携支援室より発行しています。
◆ ご意見・ご感想を以下フォームよりお気軽にお寄せください。
掲載希望の記事や研究会の案内なども受け付けています。
宛先:http://form.mag2.com/gianoubima
◆ バックナンバーは、こちらのページから読むことができます。
https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/melmaga/
◆ このメールは「まぐまぐ!」を利用して配信しています。
新規登録・解約は下記ページにてお願いします。
https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/magazine/
==========================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集/発行:
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科(ASAFAS)広報委員会
ASAFAS キャリア・ディベロップメント室
ASAFAS 次世代型アジア・アフリカ教育研究センター
臨地教育・国際連携支援室
協力:
京都大学 アフリカ地域研究資料センター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■